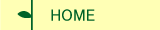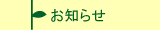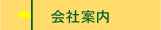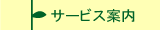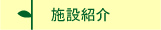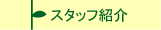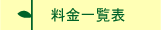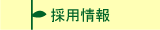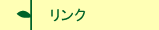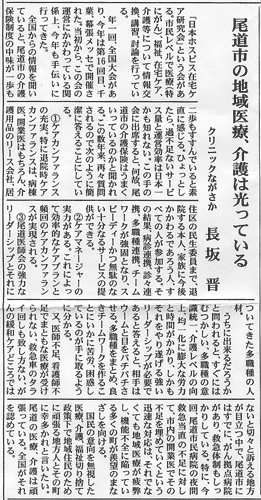 年一回、全国大会があり、今年は第16回目、千葉、幕張メッセで開催された。当初から、この会の運営にかかわっている関係上、今年も手伝いに行ってきた。 全国からの情報を聞いていると、尾道市の介護保険制度の中味が一歩も二歩もすすんでいると素直に感じる。ひょっとしたら、過不足ないサービス量と運営効率は日本一かもしれない。この手の会に出席すると、何故、尾道市の介護保険はうまくいっているのかときかれる。この数年来、再々質問されるので次のように簡潔に答えることにしている。 ①ケアカンファランスの充実。特に退院時ケアカンファランスは、病棟医、開業医はもちろん、介護用品のリース会社、居住区の民生委員まで、退院する本人、家族に今後かかわるであろう人、すべての人が参加する。その結果、病診連携、診々連携、多職種連携、チームワークが強固となり、スピーディかつ無駄のない十分なるサービスの提供ができる。 ②ケアマネージャの実力がある。これによって効率的なケアプランと頻回のケアカンファランスが実現される。 ③尾道医師会の強力なリーダーシップとそれについてきた多職種の人材。 うちに出来るだろうかと問われると、すぐにはむつかしい、多職種の意識統一、介護レベルの向上、均一化に膨大な労力と時間がかかり、しかもそれをやり遂げる強いリーダーシップが必要であると答えると、相手はウームと目をパチパチさせる。多職種をまとめ、よきチームワークを作ることにいかに苦労、困惑しているのが手に取るように分かる。 また、医師不足、看護師不足でまともな医療が受けられない、救急車のタライ回しも致し方ない、がんの緩和ケアどころではないと切々と訴える地方が目立つ中で、尾道市にはすでに、がん拠点病院があり、救急体制もしっかりしている。特に、今回、尾道市民病院の夜間救急当直の不足に対して、市内の開業医でその不足を埋めていくという迅速な対応は、それでなくても地域医療が疲弊し、機能不全に陥っている多くの町が羨望のまなざしを向ける。 国民の意思を無視した医療、介護、福祉切り捨て政策下で地域住民のために頑張る地方人とその町に幸多かれと言いたい。尾道の医療、介護は頑張っている。全国がそれを認めている。 「山陽日日新聞発表の論文を引用」(2008年7月) |